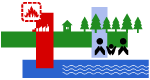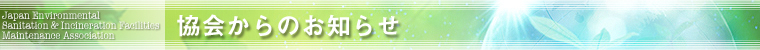
令和7年度(第38回)事業所管理者研修会開催される2025年11月20日
「第38回事業所管理者研修会」がアジュール竹芝で令和7年11月6日(木)、7日(金)の2日間にわたって、受講者100名(ごみグループ88名、水グループ12名)での開催となった。
【1日目】
はじめに上村協会会長が開講挨拶を行った。上村会長は、「環維協の事業目的は『会員相互の協力により、環境衛生施設の維持管理技術の研究・研鑽と安全で安定的な運営、作業管理の推進を通じて公共事業の使命に寄与すること』であり、この事業所管理者研修会は会社の垣根を越えて各所属会社における指導者として、その能力のさらなる向上を目指して実施しており、各講義における貴重な情報を十分にご理解いただきたい。
また、当協会を取り巻く事業環境や社会要求は時々刻々と変化しており、時代、社会環境に即した『現場総合力』の更なる向上に寄与する情報をこの研修会で得て、各事業所において指導者としての能力を十分に発揮し、広く地域社会に貢献して頂くことを切望する。」と激励された。
続いて稲田事務局長より環維協の組織と活動概要説明があり、1日目の全体研修が始まった。
<第38回事業所管理者研修会 開講> <上村会長 開講挨拶>
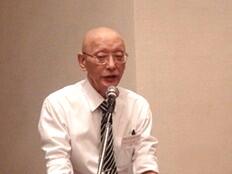

<全体研修>

特別講演 最新の廃棄物処理動向(1)
「市町村のごみ処理施設の現状と今後」
元(公社)全国都市清掃会議 荒井 喜久雄氏
ごみ処理施設は都市施設であり、円滑な都市生活や良好な都市環境を保持するために不可欠な施設であって、都市形成の骨格をなすものという話から始まり、「市町村のごみ処理の現況」「ごみ処理をめぐる環境の変化」「市町村のごみ処理の今後」等が説明され、最後に施設整備・運営の3本柱「安定性」「安全性」「効率性」に「持続可能な処理体制の確保」「資源循環の確保」「脱炭素化」の視点を付加していくことが必要であると締めくくられた。
特別講演 最新の廃棄物処理動向(2)
「プラスチック資源循環と脱炭素について」
(一財)日本環境衛生センター 環境工学第一部 次長 寺内 清修氏
プラスチック資源循環の背景として、プラスチックの問題点や気候変動問題があり、包括的に資源循環体制を強化するための廃棄物・資源循環分野の法律・計画等について説明された。次に、温室効果ガス排出削減技術の概要として、プラスチック類の分別収集・資源化、高温高圧ボイラによる高効率発電、CCS/CCUS技術等、およびこれらの施策による廃棄物処理施設への影響並びに課題について述べられ、「今後は焼却施設の集約化(広域化)を進めることが課題となる。」と講演を終えられた。
<荒井 喜久雄氏> <寺内 清修氏>


続いて、青木広報部会長より「広報部会のご案内」として、広報部会の活動内容、協会誌「環境施設マネジメント」の内容、協会ホームページについての紹介があり、昼食休憩となった。
午後からは、ごみグループと水グループに分かれ専門技術講座、事業所紹介、ごみ処理・水処理Q&Aおよびグループディスカッションが行われた。
《ごみグループ》
専門技術講座(1)
「ごみ処理施設の事故(リチウムイオン電池由来の発火・火災事故)」
(一財)日本環境衛生センター 理事 藤原 周史氏
近年、多発するリチウムイオン電池の発火・火災状況について、東京消防庁資料等によるご報告および、環境省からのリチウムイオン電池の適正処理についてご説明された。その後、市町村のトラブル事例とその対応状況、新規施設(不燃・粗大ごみ処理施設)における安全対策等について説明がなされた。
事業所紹介
「極東サービスエンジニアリング(株) 上伊那事業所」
所長 丹羽 徹氏
上伊那地域の紹介から始まり、クリーンセンター八乙女の施設概要、業務委託内容、基幹改良工事の取り組み、改善提案活動等について説明された。
《水グループ》
専門技術講座(1)
「し尿処理・汚泥再生処理と脱炭素社会」
(一財)日本環境衛生センター 環境工学第二部 課長 小林 剛氏
脱炭素化社会に関する基本的な説明があり、制度や技術を含めたし尿・汚泥再生処理における脱炭素の取り組み、今後のあるべき将来像として広域化や有機性廃棄物のメタン発酵処理について述べられた。
事業所紹介
「クボタ環境エンジニアリング(株) 伊勢広域NS事業所」
所長 永野 進也氏
施設の所在する伊勢市の紹介から始まり、施設概要、事業所での保全整備やランニングコスト低減に関する取り組み、安全衛生活動等について説明された。
<藤原 周史氏> <小林 剛氏>


・ごみ処理Q&A,水処理Q&A
研修会受講者より出された質問に対しての回答説明が行われた。
・グループディスカッション
地域毎に12のグループを編成して、自己紹介に続き第1部は「防災対策」、第2部は「事業所の課題など」をテーマに自由に討議を行った。
<グループディスカッション> <グループディスカッション>


【2日目】
2日目もごみグループ、水グループに分かれ研修が始まった。
《ごみグループ》
専門技術講座(2)
「廃棄物処理施設へのデジタル・AI活用事例」
(一社)日本環境衛生工業会 (株)タクマ 課長 松本 和正氏
廃棄物処理施設では人手不足や働き方改革への対応を背景に、省力化・効率化を目的としてAI活用が進められており、運転支援(燃焼制御、遠隔監視、選別ロボット)、受入支援(自動受付、AIクレーン)、維持管理支援(計画最適化、性能監視)等の事例が紹介された。
《水グループ》
専門技術講座(2)
「し尿・汚泥再生処理分野の現状と自動化・省力化」
(一社)日本環境衛生工業会 水ingエンジニアリング(株) 部長 若菜 正宏氏
し尿処理施設を取り巻く社会背景と制度の変遷、施設数や処理人口の推移等、し尿処理における現状や課題について説明された。また、センサーや画像解析技術を用いた自動化・省人化の実例について紹介された。
<松本 和正氏> <若菜 正宏氏>


専門技術講座(3)
「環境衛生施設維持管理業協会における環境衛生施設のBCP策定の必要性」
技術部会 アドバイザー 廣勢 哲久氏
環境衛生施設における事業継続計画(BCP)について説明された。「策定した計画を基に繰り返し訓練し、非常時にも対応できるよう準備しておくことが重要である。」と述べられた。
午前の部の最後に尾前技術部会長から環維協技術部会の活動紹介とその成果物が報告された。午後からは、労務・安全衛生管理についてのプログラムが開催され、基調講演とパネルディスカッションが行われた。
労務・安全衛生管理
基調講演(1)
「管理職のための職場の人事・労務管理 心身の健康管理と高齢者の課題」
(株)OHコンシェルジュ 産業医/労働衛生コンサルタント 後藤 桜子氏
心身の健康管理を題材に管理職としての役割について講演された。また後半では近年、課題となっている高齢者雇用における健康と安全について説明された。
基調講演(2)
「“安全ルール”を守って労働災害を防止する」
神鋼環境メンテナンス(株) 顧問(社会保険労務士) 茶園 幸子氏
「安全に作業をするためにルールがあり、安全ルールは分かりやすく、理由を含めて説明することで理解が深まり、遵守される。」と労働基準監督官の観点から人の特性を踏まえた安全管理を実施していくよう講演された。
基調講演に続いて「事業所の労務管理・安全管理」およびサブテーマとして「健康上の配慮が必要な従業員への対応」「安全ルールについて」を題材にゲスト、パネラーに加え、受講者の質問も交えて、パネルディスカッションが行われた。
<後藤 桜子氏> <茶園 幸子氏>
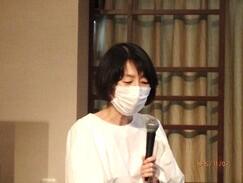

<パネルディスカッション>

井上部会長により「講義やグループディスカッションで得られた成果を持ち帰り、事業所の運営に役立てて欲しい。」と研修の講評と閉会の辞が述べられた。続いて修了証を代表者に授与し、閉会となった。
<井上安全衛生部会長 閉会挨拶> <修了証授与>


※研修会の詳細については、「環境施設マネジメントNo81」(2026年3月発刊予定)に掲載します。